TX 運賃改定答申・審議会資料を見る
TXの上限運賃変更認可申請は、6月26日、運輸審議会から認可適当の答申が出た。今回はこれを見ていこう。運輸審議会が鉄道局の見解に食いついた珍しい審議だと思われる。
「首都圏新都市鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案」に関する答申について
(資料)運輸審議会 諮問関係事案の審議状況(最新年度のところなので令和7年度をクリック)
申請時の論点
4月14日に書いた弊記事をここに置いておく(リンク)。
特に目玉となるのは、「小児普通運賃はIC運賃である1円単位運賃を上限200円に設定」、「子供通学定期は上限を5000円に設定」「3か月、6か月定期の割引率を引き下げ」である。このあたりが話題にあがるのであろうと思ってみていた。
パブリックコメントでの回答(第3回資料)をみてみると、
・「子育て世代が沿線に定着することは、つくばエクスプレス線及び沿線の発展にとって重要であるとの考えから、運賃施策において子育て世代の負担軽減を図ることを明確に打ち出すべく」「日本全体で少子化が進行するなか、子育て世代が沿線に定着することは、つくばエクスプレス線及びその沿線の発展にとって重要であると考えている」との回答で、特段これについて運輸審議会委員が諤々議論しているわけではなかった。
・小児運賃のIC化率は大人の96%に比べて低い74%。また、上限200円の対象となる14キロ以上の輸送人員のは、そのうち、38%であるとしている(第2回44ページ)。
「事業報酬」に関して
答申での記載
しかし、普段かなり画一的な書式になっている運輸審議会の答申では、敢えて触れられているものがあった。まずは答申を引用する。
また、申請者は大手民鉄等事業者に該当しないため、所管局において、中小民鉄事業者の収入原価算定要領に基づき審査している。
(中略)
配当所要額(適正利潤)は、中小民鉄事業者の収入原価算定要領において、払込資本金に対し10%配当に必要な額の鉄軌道事業分担額を計上するものとされており、これに基づき算定すると、配当金約185億円に加え、法定準備積立約19億円、法人税等約100億円を含め、合計約303億円であることを確認した。
(中略)
一方、申請者においては、多額の事業費等に見合う自治体等からの出資金を受け入れたことから、その事業規模に比して資本金が巨額であるため、配当所要額(適正利潤)が多額となっているが、配当の実績や計画がないこと、算定された法人税等については実際の支払予定額とは大きく異なることを確認した。
(中略)
これに関し、中小民鉄事業者の収入原価算定要領における配当所要額(適正利潤)算定の趣旨を所管局に確認したところ、中小民鉄事業者の中には大手民鉄等事業者に比べ自己資本等の財務基盤が脆弱な事業者が多く見られることから、内部留保の充実により財務体質を改善する必要があるため、との説明があった。上記の申請者の実情及び中小民鉄事業者の収入原価算定要領の趣旨を勘案すれば、同算定要領に基づき算定された配当所要額(適正利潤)を基に本事案を審議した場合、申請者の経営状況等の実態に即した判断とならないことが懸念されたため、追加的な検証を行うこととした。
(中略)
具体的には、申請者の営業収入、営業キロ、輸送人員等が大手民鉄事業者に準ずる規模であることを踏まえ、所管局に対してJR旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業者の収入原価算定要領(以下「大手民鉄等事業者の収入原価算定要領」という。)を適用した場合の事業報酬等の算定を求めたところ、所管局から、事業報酬は約163億円、法人税等は約62億円との試算が示された。
どういうこと?
まあ長いですね。一つずつ確認していく。
鉄道事業法16条2項は、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうか」を審査して上限運賃の認可を行うとしている。
じゃあ、この「適正な原価」「適正な利潤」あるいは「収入」をどう仮定して審査するのか。これを通達で補っていて、それが「JR・大手民鉄・地下鉄」と「それ以外(中小民鉄)」に分けられています。TXは後者、中小民鉄に該当する。
算定要領は、前者のほうが細かく、かつ他社との競争要素を含んだ算定で、中小民鉄のほうは、個別事情に配慮し、「適正に」だとか「増収努力を見込んで」だとかいう言い方で決められている。
さて、上記で触れられていた「配当所要額」「事業報酬」などというのは、こういう計算をしている(法人税の支払い見込み額もこれらを基礎に算定している)。
【JR・大手民鉄・地下鉄】
レートベース(法定債務除く事業資産)に、報酬率(自己資本報酬と他人資本報酬を30:70で按分)を掛けて計算する
【中小民鉄】
払込資本金に対し10%配当に必要な額の鉄軌道事業分担額
ここにいう10%配当は、どうやら「額面配当」なるものを前提していたようなので、まあわかりにくい(参考リンク)。額面株式なんて平成13年廃止なので私が生まれる前の話ゆえどうしようもないです、すみません。また、大手民鉄も10%配当を継続的にしていたというのも理由であるとのことである。
TXの例について
中小民鉄の場合、「払込資本金に対し10%配当に必要な額の鉄軌道事業分担額」が適正利潤となると説明した。TXの場合、配当所要額は、具体的には、以下のような計算式になるのである(第4回資料)。
配当所要額=配当額(資本金の10%)+法定準備金積立(配当金の10%)+法人税(配当所要額の23.2%)+地方法人税(法人税の10.3%)+県民税法人税割(法人税の4.7%)+市町村民税(法人税の8.4%)+事業税所得割(配当所要額の11.8%)+事業税地方法人特別税(事業税所得割の260%)
これは配当所要額についての一次方程式とみて…
配当所要額=資本金×0.11÷0.671232
資本金は1850億円だから、配当所要額は303.47億円
TXの申請時資料(パブコメ)をみると、確かに配当所要額は年303億円(配当金約185億円に加え、法定準備金積立約19億円、法人税等約100億円)として、算定されている(一方原価は年420億円程度、収入は改定前は490億円程度、改定後は550億円程度とされている)。
TXの資本金は1850億円(cf.JR東日本の資本金は2000億円である)である。高額となった建設費について多額の出資(整備費見合いとして)がなされたため、事業規模に比して巨額の出資となっている(第2回資料29ページ)。これの10%は確か185億円である。また、別に三セクでも10%配当を実現している会社はあるのである(北急など、第2回33ページ)。なお、減資については考えていないとのことである(第4回資料)。
しかし、実際にはTXは無配である。もっとも、鉄道局としては、JRTTへの建設費償還のために、毎年200億円を支払っているのだから合理的な範囲であるとしている。
また、法人税・法人税等調整額をみてみれば、2024年度は12億円しか払っていない(EDINETに提出された資料、令和5年度は9億円であることについて、第4回資料)。そうなると、実勢とかけ離れた数値とになり、運賃改定の余地が実勢よりも高いということになってしまう。いずれにせよ、実際の額とのかけ離れていることだけは確かである。
大手私鉄とみなす
大手民鉄の場合、「レートベース(法定債務除く事業資産)に、報酬率(自己資本報酬と他人資本報酬を30:70で按分)を掛けて計算する」を計算するとなった。
これをもし、TXを大手民鉄とみなして、事業報酬の部分を算定すると以下の通りになる(第5回資料)。
まず、TXの事業資産は、令和5年度実績で、5813億円となり、ここに報酬率2.8%を掛けると事業報酬は163億円となる。ここに法人税(課税標準も事業報酬を基礎に計算する)61億円を加えると、225億円程度となった。
要は原価+利潤≧収入であることには間違いなさそうだとして、今回は認可適当の答申となったようである。
もっとも、要望事項で、
中小民鉄事業者においては、その事業規模や経営形態等が多様であることや、大手民鉄等事業者におけるヤードスティック方式のような事業者の効率化努力を促すための仕組みもないことを踏まえ、その運賃改定申請の審査に当たっては、当該事業者の経営状況等の実態に即した審査が行われるべきものと考えるので、そのための方策について検討されたい。
と書かれているので、こういう事態は避けるべきという議論は出てきそうである。
そのほか
・給与についてベースアップを見込まない理由
・経営効率化策(保有車両数に比して効率的な運営であること、輸送人員に比して現業職員が大手民鉄並みに少ないこと、その他の生産性向上施策:第5回が詳しい)
そのほか、大きな論点表はこちらにある。
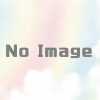

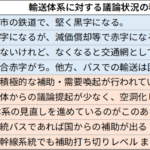

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません