なぜ令和も7年なのにブログをやっているのか?
さて、本ブログも足掛け6年、本格的な執筆を始めてはや5年、投稿本数もいよいよ大台の1000本が目の前に迫ってまいりました。自戒も込めつつ、一つ読者からありそうな質問に答えておきましょう。すなわち、この令和も7年になるというのに、なぜ私はブログという媒体での活動を主としているかということである。
答えとしては、「ほかの方法に比べて自分が向いているから」という身もふたもないというものになると思われる。①自分のやりたいことが文字媒体に一番向いているということと、②自分の能力が文字媒体に向いているということの2つに大別できるものと思われる。
自分のやりたいこととの相性
一応これでも大学(院)生の端くれである。だとすれば、科学的プロセスに則ってなにかを言明するということ自体にはなれているはずであり、まさしくその通り行動しているというところである。
もう少し突っ込んでいうなら、旅行記を書くこともあるけれども、メインの活動ではない。そして、YouTubeに旅行動画を挙げるわけでもない。そもそも旅行中に動画をまわすということもなく、もっとぼーっとしている。何なら旅行記を書くことを前提に写真を撮っていたのに、旅行から日程が経ってしまいボツになった回が何度かある。そのうち、ボツ集に上がるかもしれません…
撮り鉄もできないと表現の幅としては弱い(特にブログでもサムネが重要であったり、文字ばっかりではなく、画像が多くあることが読みやすさのコツであることはご承知おきのとおりである)。でも、やっぱり自分の書いた原稿を読んでほしいよしいし、あくまで文字ベースでやりたいという意図もかなり強い(コタツ記事との謗りは甘んじて受け入れるとして…)。
鉄道×なにか(=公共交通?経営?)などの類聚であったりのものを動画で挙げておられる方ももちろんいるし、YouTubeでそういうのを企画にされている方がいることも知っている(例えばおもしろ地理さんなんかがその傾向として非常にわかりやすいだろう)。じゃあやりたいことが先に述べたようなものだから、必然的に文字媒体なのか…と言われるとそれだけじゃないというのが次の話。
自分の能力との相性
みなさんはYouTube・niconicoに動画を投稿したことはあるだろうか。それも、撮って出しではなく、プレビューなり、AviUtlなり、プレミアプロなりで編集して投稿したことはあるだろうか。私も、カットとテロップを付した程度の動画を作成したことがある。あれって、もちろん慣れや製作上の知恵などの蓄積などがないからというのもあるが、滅茶苦茶時間がかかるわけで、平気で数時間溶けるわけである。カットとテロップだけでも苦しむのに、音MADなんかで何十レイヤー使ってるんだというものは編集にかかる時間だけでなく、エンコードにどれだけ時間がかかってるんだという話になる。しかも旅行系の動画を挙げておられる方であれば、特に、常に旅行に際して動画をまわし続けねばならず、旅行してるのか編集してるのかがわからないということもあるようである。もちろん彼らの創作に対して最大限の敬意を示さねばならぬわけだが、じゃあ私がメインで注力すべきかと言われれば違うということもまた同時にわかるわけである。
(鉄道などの)イラストについても同様である。経験値の不足もあるが、空間把握能力・観察力・細部に気を遣う力など、根本的に欠けていることは既に重々自覚している。そしてコミケ1月前のTLなどを見れば明らかなように皆締切に追われているわけであるが、そこでの筆のスピードの速さというのは目を見張るものがある。
じゃあ一方で、私のブログはどうか。ここまで、およそ1500字ほど連ねてきたが、おおよそ10分~15分ほどで書きあがっている。明らかに書くスピードが上がっているのである。そして、例えば書き連ねてきた記事が多数あるので、過去はどうだったっけということを引っ張ってこればあら不思議、時事ネタでも記事の骨格がすぐ出来上がるのである。ここは経路依存性もあるのだが、書けば書くほど記事のクオリティが自動的に上がる仕組みなのである(前回見たようにとリンクを張るか要約すればいいのである)。
とはいえ言い訳するな
はい。ここまできて読者の7割が思っておられることでしょう。動画制作も撮り鉄もイラストも逃げてきただけではないのかと。それは確かに仰る通りであって、だからこそ逃げた先でうまいこと活路を見出して、歴戦のブロガーの方々のいるレッドオーシャンに食らいついているともいえる。とはいえ、動画制作がある程度できたほうがよい(せめて効果的な表現であったり、喋り方であったり、録り方であったり)し、撮り鉄にしても、せめてブログにおいて、説明に供するに足りる程度の写真は撮れるほうがよいし、撮りに行くべきであろうと思うし、イラストも説明に必要な範囲だとしても書けたほうが良いことは明らかである。
結局なんの話かと言われれば、得意な表現があることは認められるにしても、「表現の幅」という紛れもない冷徹な現実があるわけで、そこから目を背けることだけは避けなければならないということである。
というわけで、深夜テンションで自分に向き合った回でございました。


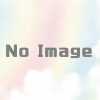


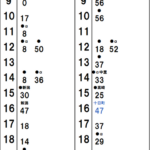

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません