美祢線 復旧方法の取りまとめ JRはBRTを推す
中国新聞の報道によれば、美祢線の利用促進協議会において、被災した美祢線の復旧方法の検討結果をまとめた報告書が出たということである。
山口の美祢線復旧「BRTが適当」 JR西日本、利用促進協議会で見解 7月に意見集約へ
【追記】美祢線利用促進協議会復旧検討部会(一番下にとりまとめ結果が載りました)
美祢線は、2023年7月の大雨により、代行輸送が実施されている(リンク)。2024年10月からは快速バスの実証運行が実施されていた(弊記事)が、2025年3月ダイヤ改正をもって運行を終了している(リリース、なお実際には1往復増便している)。
一方で、復旧に向けた議論は、復旧後の利用促進策については先にまとまっている(利用促進協議会WG)が、肝心の復旧方法が決まっていない。復旧検討部会(2025年2月の第4回資料)の資料を見る限り、鉄道(直営かみなし上下分離か三セクか)、BRT、バスという選択肢が出ており、それぞれについて、復旧の際の運行本数(BRT、バスは1.5倍を想定)、乗降場所の柔軟性、バリアフリー性、災害を再び受けた際の復旧の容易さ、国庫補助、コストを比較検討している。
今日提出された報告書はまだ確認できていないが、報道を見る限り、2025年2月にJRが提出した資料に近いと思われるのでそれを確認すると、BRTについては阿保駅から湯ノ峠駅手前の貞任第5踏切(以南は国道316号線を利用)までの4.2kmを鉄道用地から転用し、専用道とするものを基本としている。BRTの復旧であれば、この専用道以外は2年ほど、専用道を含んで3~4年で復旧可能とみている。イニシャルコストは55億円、ランニングコストは年2.5億円とみている。なお、この際、JRとして「鉄道と同等の運賃サービス・時刻表や運行情報の一体化など鉄道との親和性を高めることを目指す(資料より)」ことを明言している。
一方、鉄道での復旧であればイニシャルコストは58億円以上、ランニングコストは年5.5億円以上、復旧は最短でも10年とみている。
これらを踏まえると、BRTでの復旧(恐らく路線網の中での位置づけは日田彦山線に近いとみてよい)が一番楽ではあろうと思われる。少なくとも、JRとして「南北を結ぶ交通軸として、利便性と持続可能性を確保した地域公共交通の復旧は必要(資料より)」としていること、鉄道とのモード間に障壁を埋めようという姿勢を見せていることから、これが優勢であろうと言わざるを得ない。

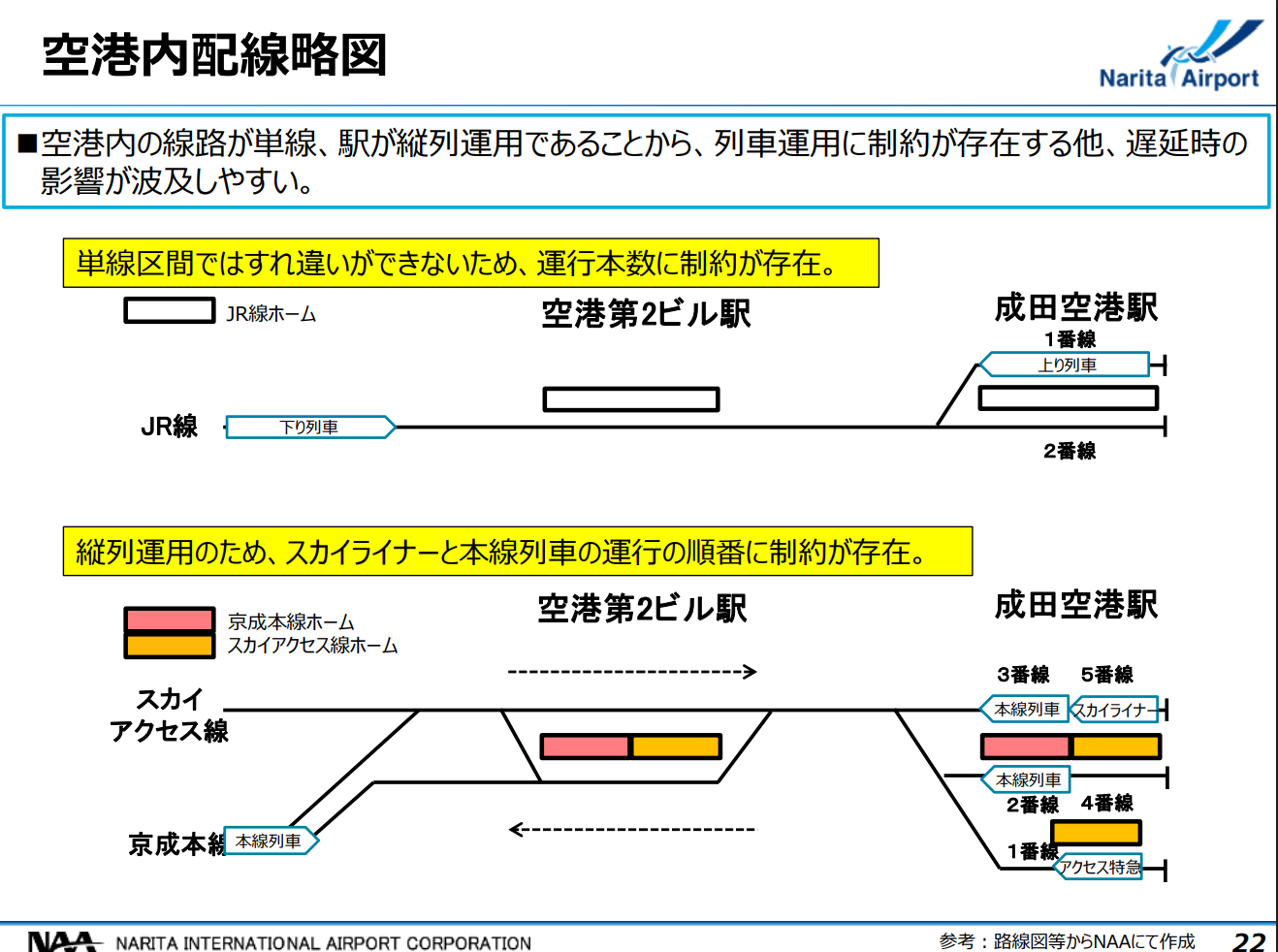
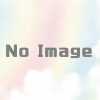



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません