【ついに】建設前加算運賃制度を新設へ
国土交通省鉄道局は、パブリックコメントにおいて、「供用開始前後において加算運賃を設定する際の取扱いについて」に関する意見募集を実施している。期限は9月9日までである。なお、国交省HPにリリースはない。
「供用開始前後において加算運賃を設定する際の取扱いについて」に関する意見募集について
いわゆる「新線加算」や、「総括原価方式(単純な値上げ)」との違いを意識しながら内容をみていこう
内容は?
〇供用開始前の加算運賃設定を認める。
〇その根拠は鉄道事業法16条2項、軌道法11条である(総括原価方式、新線加算も同じ)
〇その際「適正な原価」は対象となる設備投資についての減価償却費
〇「収入」はその50%を超えないことを審査する
〇一般的な運賃改定(総括原価方式)も併用できる
〇対象となるのは速達性向上、定時性向上、快適性向上につながるもので、新線整備に限らず、複線化・複々線化、駅改良、交換設備改良、高速化、車両基地整備、長編成化も認められる。
〇加算設定区間は、設備の結果、利便性向上が認められる区間に限られる
〇加算運賃収受機関は原則10年以内とする
〇鉄道事業法上の審査においては、算定期間は3年とする(総括原価方式、新線加算も同じ)
〇利用者に対して必要な情報提供、透明性のある資金管理、進捗状況の公表を求める
〇供用後の加算運賃設定も概ね同様である。
〇供用開始後の「適正な原価」は供用開始前に前倒ししたものを差し引く
〇新線整備に伴う加算運賃を設定する場合は、(私が理解する限り)従前どおり
〇本制度は第一種鉄道事業や上下分離方式に限定されない
〇国交省への資料提出、進捗状況の報告は当該年度の6月末までに行うものとする。
これまでの検討など
現在の種々の制度の議論の起点は2016年の交通政策審議会答申(東京圏における今後の都市鉄道のあり方について)であろうと思われる。それ以降。2017~18年にかけて、「都市鉄道における利用者ニーズの高度化等に対応した施設整備促進に関する検討会」が行われていた。更に、2022年にかけては、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会において、「鉄道運賃・料金制度のあり方に関する小委員会」、2024年には、「今後の都市鉄道整備の促進策のあり方に関する検討会」が置かれ、更に議論が高度化されていた。結果的には今後の都市鉄道整備の促進策のあり方に関する検討会に出ているのと同じ表が使われていたので、これが決定打ということでよかろう。
バリアフリーについては、バリアフリー料金加算制度として実現している。また、変動運賃制度(JR西の新電特、JR東のオフピーク定期券制度)や、運賃変更認可の際に研究開発費をヤードスティック(他社比較)対象外にするなど、鉄道事業者にとって有利な制度が増えてきたところである。
過去には、「特定都市鉄道整備積立金制度」で特別加算制度が認められていた。現在でも、特定都市鉄道整備工事であると認定されているもの(野田線複線化、池袋線複々線化など)もある。工事区間外でも、混雑緩和が見込まれる場合には加算ができる制度であった(例:日吉~多摩川間複々線化、目黒線立体交差化の際に、東横線も混雑緩和が見込めるということで特別加算の対象になっていた)。しかし、法人税の優遇がないために、これ以降活かされることはないとされている。またそもそも、工事規模の要件などもあったので使いやすい制度ではない。また、既存ストックを活かした利便性向上として、都市鉄道利便増進事業費補助(新横浜線や蒲蒲線が対象のそれである)もあるが、第三セクター・JRTTを対象とするものである。
そして、広く利用者に負担を求める制度は限られていたといえる(参考資料)。新線建設に係る加算運賃制度は、確かに利用者負担を求められるものだが、新線部分に開業後にしか設定できない(しかも中之島線のように既存線と並行している区間を敢えて除外するなどの配慮をしている場合もある)ため、既存路線への改良へ使える制度がなく、基本運賃で何とかするしかないということになっていた。
利用者負担制度としては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度、電気通信におけるユニバーサルサービス交付金制度、空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料、下水道における受益者負担金、道路整備財源など、他の業種であればそれぞれ実情に合わせた制度があるところである。今回の供用開始前の加算運賃設定はそれに値するものに化ける可能性がある。もっとも、ネットワークは1事業者で作られていないから、その点については中々難儀なことも発生するかもしれない。ただ今のところ、狙い撃ちにされていそうなのは中央線複々線化のようなプロジェクトであると思われる(もちろん国は明示していない、私見である)ので、そこは期待したいところ。
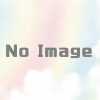




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません